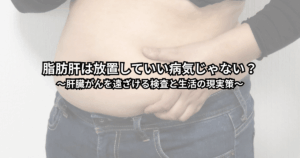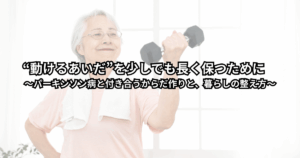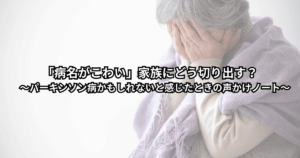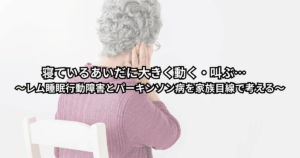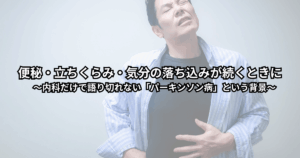高齢の家族が「少し飲んだだけなのにフラフラする」「この薬を飲むと一日中眠い」と話すと、心配になりますよね。同じ量でも若い頃とは効き方がガラッと変わるのが、高齢期のからだの特徴です。ここでは、年齢とともに体内での薬の動き方がどう変わるのか、「効きすぎ」のサインと家族ができる見守りポイントを、できるだけイメージしやすい形で整理していきます。
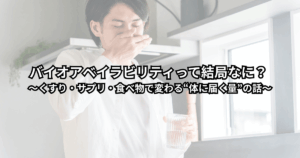
1. 「前は平気だったのに…」高齢の家族に増えてくる薬の悩み
家族の通院に付き添っていると、気づけばおくすり手帳が何ページも埋まっている、ということがあります。血圧・コレステロール・糖尿病・骨粗しょう症・睡眠・痛み止め…気がつくと、朝だけで5錠以上という方も珍しくありません。
そのなかでよく聞く声が、
- 「飲み始めてから立ち上がるとフラッとするようになった」
- 「ごはんを食べる気力がわかない」
- 「前よりぼーっとして転びそうで怖い」
といった、「効きすぎ」を疑いたくなる変化です。
実際、高齢者では薬による有害事象(いわゆる副作用)は若年者の約2倍、薬が原因で救急受診・入院になる頻度は約7倍という報告があります。長寿科学振興財団+1
つまり、「ちょっと効きすぎかな?」という感覚は、決して大げさではありません。
この記事では、高齢になると薬が効きやすく・残りやすくなる理由と、「どんな様子があれば相談した方がいいのか」を、家族目線で整理していきます。
2. 「薬が効きすぎる」ってどういう状態?ざっくり整理してみる
「効きすぎ」と聞くと、強い薬を飲み過ぎたイメージを持つかもしれません。ただ、現場でよく問題になるのは「量が多すぎる」というよりも、「からだの変化に対して、今の量が合わなくなってきた」という状態です。
イメージを整理すると、次のような感じです。
| 状態 | からだのサインの例 |
|---|---|
| 薬が効きにくい | 症状がほとんど変わらない・むしろ悪化している |
| 薬がちょうどよい | 症状が和らぐが、生活への支障は少ない |
| 薬が効きすぎる | ふらつき・眠気・食欲低下・便秘などが強く出る |
高齢の方でよくみられる「効きすぎ」のサインは、例えばこんなものです。
- 立ちくらみや転びそうなふらつきが急に増えた(血圧降下薬・睡眠薬・抗不安薬など)
- 以前よりも昼間の眠気が強く、ぼんやりしている時間が増えた
- 便秘・食欲低下・吐き気が続き、体重が減ってきた
- 夜間のトイレ回数が増えて、疲れ切ってしまう
もちろん、これらがすべて薬のせいとは限りません。ただ、「薬を増やしてから」「新しい薬を飲み始めてから」こうした変化が出てきた場合、からだの中での薬の動き方が変わっている可能性を考える価値があります。
世の中では「バイオアベイラビリティ」という言葉で、飲んだ薬がどれくらい体内で使える形になっているかを表現します。高齢になると、この“体に届き方”そのものが若い頃と変わってくるのがポイントです。
3. なぜ高齢になると薬が効きやすくなるのか?からだの中で起きていること
ここからは少し中の話です。「構造」「臓器の働き」「感覚」の3つの視点で、高齢者の薬の効き方を眺めてみます。
加齢とともに変わる「薬の通り道」
飲んだ薬は、ざっくり言うと「吸収 → 分布 → 代謝 → 排泄」というルートを通ります。この流れのあちこちに、加齢の影響が出てきます。
1つ大きいのが腎臓と肝臓の変化です。
腎臓の血流量は、30歳ごろを100%とすると、80歳では約50%程度にまで下がるとされています。日本腎臓学会
腎臓は多くの薬を尿として排泄する“出口の役割”を担う臓器なので、勢いが弱くなると薬が体に長くとどまりやすくなります。
肝臓も、加齢とともに代謝する力が少しずつ落ちることが知られており、「同じ量を飲んでも、分解が追いつかない」状態になりやすくなります。厚生労働省+1
さらに、加齢によって次のような変化も起こります。
- からだ全体の水分量が減り、脂肪の割合が増える
- 筋肉量が減ることで、薬の“分布の仕方”が若い人と変わる
- 脳や神経が刺激に敏感になり、同じ量の薬で眠気・ふらつきが強く出る
こうした変化が重なると、「若い人にはちょうどいい量」が、高齢者には“効きすぎ”になってしまうことがあります。
高齢者の薬物有害事象が増えやすい理由
高齢者では、複数の病気を抱えていることが多く、薬の数が5種類以上になる「ポリファーマシー」になりやすいとされています。厚生労働省の指針でも、65歳以上、とくに75歳以上の高齢者では服用薬の種類が増え、薬物有害事象が起こりやすいことが指摘されています。厚生労働省+1
別の報告では、高齢者の薬による有害事象の頻度は、若年者の約2倍、薬が原因の救急入院は約7倍というデータもあります。長寿科学振興財団+1
薬が多くなると、
- 作用が重なって「眠気+ふらつき」が強く出る
- 互いの代謝を邪魔しあって、血中濃度が予想以上に上がる
- どの薬が原因か分かりづらく、対応が遅れる
といったことが起きやすくなります。
「感覚」も変わるから、家族の目が大事
もうひとつ大切なのが、感覚の変化です。高齢になると、自分のからだの変化に気づきにくくなることがあります。
- 軽いふらつきや眠気を「年のせい」と思ってしまう
- 便秘や食欲低下が続いても「よくあること」と気にしない
- 逆に、不安が強くなり「薬を減らしたら怖い」と感じる
その結果、「効きすぎ」のサインが見過ごされ、気づいたときには転倒・骨折・せん妄(急な混乱)といったトラブルにつながることもあります。私自身、リハビリ現場で「薬を見直したら急に頭がスッキリして動けるようになった」というケースを何度も見てきました。
4. 生活パターンの中で起きやすい「効きすぎ」と、家族にできること
薬が効きすぎる背景には、年齢だけでなく生活リズムや飲み方のクセも関わります。よくあるパターンをいくつか挙げてみます。
よくあるパターンの例
- 脱水ぎみの日に、いつも通り血圧の薬を飲む
発熱・下痢・食欲不振などで水分が足りていないときに降圧薬を飲むと、血圧が下がりすぎてふらつきや失神のリスクが高まります。 - 複数の医療機関から似た薬が出ている
かかりつけ医と専門医、複数の病院を受診していると、同じ系統の薬が重なって処方されることもあります。おくすり手帳を見比べると「似た名前の薬が2種類入っていた」ということも。 - 飲み忘れをまとめて飲んでしまう
1回飲み忘れたからといって、次に2回分まとめて飲むと、血中濃度が急に上がり、「効きすぎ」の状態をつくりやすくなります。
こうした生活パターンとからだの状態が組み合わさると、「いつもと同じ量なのに、今日は効きすぎた」という日が生まれやすくなります。
「start low, go slow」という考え方
高齢者の薬物療法では、「少ない量から始めて、ゆっくり増やす(start low, go slow)」という考え方が国際的にも推奨されています。CareNet Academia+1
これは、からだの変化を見ながら、必要最小限の量を探していくという発想です。
家族としてできるのは、この考え方を頭の片隅に置きつつ、日々の様子を医師や薬剤師に伝えることです。「この量はちょっと強すぎるかも」という生活目線の情報は、処方を調整するうえでとても大切な材料になります。
Q1. どんな様子があれば「薬が効きすぎているかも」と考えた方がいいですか?
目安としては、次のような変化が急に出てきたときです。
- 立ちくらみや転倒が増えた
- 日中の眠気が強く、会話中にウトウトしてしまう
- 便秘・食欲低下・吐き気が続き、体重が減ってきた
- 夜間せん妄(夜だけ混乱する・見当違いな言動)が出てきた
とくに「薬を増やしてから」「新しい薬に変わってから」こうした変化があれば、効きすぎを疑って医療者に相談してよいと思います。
Q2. 心配なとき、家族が勝手に薬の量を減らしてもいいのでしょうか?
自己判断で量を減らしたり、飲む回数を飛ばしたりするのはおすすめできません。症状が急に悪化したり、かえって危険になる薬もあるためです。
大事なのは、「こういう変化が出ていて心配です」と具体的な様子をメモして、受診時にまとめて相談することです。電話で薬剤師に聞いてみるのもよい方法です。
Q3. どのくらいつらくなったら、受診や相談を急いだ方がよいですか?
次のような場合は、早めの受診や医療機関への連絡をおすすめします。
- 意識がぼんやりして会話がかみ合わない
- 立ち上がるたびにフラフラして歩けない
- 息苦しさ・胸の痛み・強い頭痛などが出てきた
- 吐き気や下痢が続き、水分がほとんど取れない
「いつもと違う」と家族が感じたときは、念のため相談しておく方が安心です。
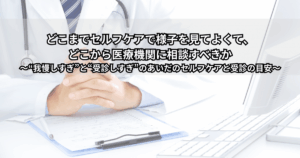
5. 今日からできる「ちょうどいい量」に近づくための小さな工夫
最後に、家族として今日からできる工夫をいくつか挙げてみます。全部でなくて構いません。できそうなものから1つ選ぶイメージで読んでください。
- おくすり手帳を“情報のノート”として育てていく
いつ、どんな薬が追加・変更されたかだけでなく、「この薬を飲んでから眠気が強い」などのメモを家族が一緒に書いておくと、医師も調整しやすくなります。 - 「効きすぎかも?」と感じたサインを3つ決めておく
例えば「ふらつき」「昼間の眠気」「食欲の変化」など、見守りのポイントを決めておくと、変化に気づきやすくなります。 - 体調が崩れたときの“合言葉”を共有しておく
発熱や食欲不振の日は、「いつも通り飲んでいいのか不安になる」ときがあります。そういう日は「自己判断せず、まず電話で相談する」といったルールを家族内で決めておくと安心です。
薬は、上手に使えば生活の質を支えてくれる強力な味方です。一方で、高齢期には「ちょうどいい量」の幅が少し狭くなるため、家族の気づきと見守りがいっそう重要になってきます。
「飲んでいれば安心」ではなく、「今のからだに合った量になっているか」を、ときどき一緒に見直していけると良いですね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事があなたのより良い生活のための一助になりますように。